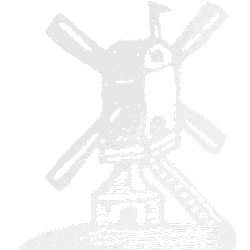明日は月曜日で休み。
休み前には、店の帰りにガソリンスタンドに寄って満タンにする。
いつも寄っているスタンドはセルフサービスだ。
3,000円入れると必ずおつりが出ていたのに、ここのところおつりがない。
そして今日、おつりが出なかった上に、メーターも上限に達せず、まだ数ミリあいている。
ぼくの車は燃費がいいからまだいいけど、燃費の悪い車に乗ってる人はつらいだろうな。
秋の扉
海で泳いでいると、急に水が冷たくなって不安になることがある。
ぼくはいつものように机に向かって読み物をしていた。
時計の針は午前0時を回ろうとしている。
突然、カーテンが大きくひるがえった。そしてぞっとするほど冷たい風が吹き込み、一瞬にしてそれまでなかった気配が部屋を占領した。
なにか得体の知れぬものが部屋に入ってきた様子である。
ぼくは逃げるように階段を降り、台所で水割りを飲みながらしばらく待っていた。
秋分の日
いろんな祝日があるけど、気に入っているのは春分と秋分の2つだけ。
春分と秋分は祝日なのに、夏至と冬至が祝日じゃないのはなぜだろう。
一番好きなのは冬至。この日を境に日が長くなり始める。
太陽と地球の関係を示している祝日、それが春分と秋分。
壮大でロマンチックな祝日だよね。
残暑
臆面も無く暑い日は続く。
ぼくがこんなことをいうのもどうかと思うけど、ホット用のコーヒーがよく売れる。
こんなに暑いのに、お客様は毎日熱いコーヒーを飲んでらっしゃる、と思われる。
文化人なんだなぁ。と、妙に感心したりする。
江ノ島の空
天気のいい日が続く。空はコバルトブルー。
今から25年ほど前の話。
免許取立てのぼくに、悪友が「いい話」と称してアルバイトの話を持ってきた。
鹿児島から江ノ島までヨットを運ぶのだが、その運転手を探している、というものである。
ぼくは東京が好きだった。誘われればいつでも行く。
「いいよ」
話は決まった。
友人とかわるがわる運転しながら丸一日かけて走った。
なんの目的もなしに来てしまった江ノ島。今でも時々思い出す。空が青かった。
なぜか、漠然とした悲しみがいつまでもぼくを捕らえて離さなかった。
今でも機会があるたびに、一人で江ノ島に行く。
あの時と同じように空を見あげ、あの悲しみの余韻がどこかに隠れてないか探そうとするが見つからない。
カタルシス
残暑がきびしい。
今日も33度まで上がったらしい。
だからといって、今度の週末、海に行って泳ごうという気にはならない。
名ばかりの秋。やぁね。
しかし、体内時計はパーフェクトに秋モードになっているようだ。
「人生」とか「愛」といった大きなテーマについて考えるフリをしたくなる。
昨日、衛星放送をなにげに見てたら、海の夕焼けを背景に、カヴァレリア・ルスティカーナが演奏されていた。
みるみる引き込まれてしまい、不覚にも涙がこぼれそうになった。
人生、愛、悲しみ 喜び。
秋だな。
十六夜
月曜日なので今日も休み。
昨夜は十五夜。夕焼けの中、屋上でビールを飲みながら月の出てくるのを待った。
妖しい色に染まった月がのぼってきた。
今日は十六夜。屋上でバーベキューをした。
月が出てくることなど忘れて四人の家族は肉を焼き、ビールを飲んだ。
ふいに、だれかが思い出したように言った。「あっ、今日は十五夜だよね」
「あ、そうか、今日は十五夜だったね」と、昨夜いっしょに十五夜を見た某ヨッパライが同意した。
負けたよ、キミたちには。ぼくは敗北した。
しばらくして東の空に丸い月が浮かんだ。
十五夜
今日は第三日曜日で休み。
朝から思い切り晴れている。しかし、ドライブに行く気はない。
普段、平日に休んでいると、わざわざ人出の多い日曜日や祝日に出かける気がしなくなる。
だからといって、何もせずに家でうろうろするのもつまらない。
ふと、店のガスレンジが壊れているのを思い出した。
何度プロを呼んでも治らず、あげく、「これはハズレ品ですね」とサジを投げられた可哀想なレンジである。
いったん点火するものの、すぐ消えてしまう。おそらく、失火センサーの不具合だろう。
ぼくはドライバーを片手に愛情を持って修理を始めた。
センサーの不具合、それはつまり感じないか、感じすぎるか、である。
ぼくは感じるところを、つまりセンサーを優しくナデナデするところから始めた。
問題点を想像しながら調整すること約10分。
見事に着火するようになった。新品でもこうはいくまい、と思える完璧さでバシバシ着火する。
愛はレンジをも救う。
明日は定休日
今日はお客様が多かった。
「明日と明後日はココお休みでしょ?だから買いに来たのよ」
常連のお客様が口々にそうおっしゃる。
オープンして丸五年。思えば短いようで長かった。
やっと…やっと第三日曜日が定休日であることを憶えていただけたらしい。
うれしかった。