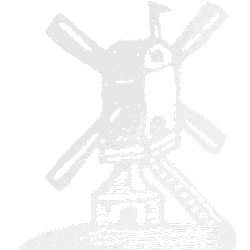To say Good bye is to die a little
さびしい夏の夜

風呂から上がって屋上に上がり、フェンスにもたれて夜景を眺めていた。遠くで灯台が点滅しているのが見える。風が気持ちよかったので、時を忘れて夜景に見入っていた。が、ふと、どこかおかしいような気がしてきた。何かが足りない。でもそれが何なのか分からない。なんだろう。虫の声は聞こえる。夏の夜だから。そうだ、前の通りの外灯に虫がいない。いつもなら、こんな夏の夜、虫たちが外灯のまわりでお祭り騒ぎをしているのだ。それがまったくいない。外灯のまわりは通夜のようにひっそりしている。昨年の暮れ、家の前の通りの外灯は全部LEDランプに付け替えられた。原因はそれだった。LEDランプに虫は寄ってこないのである。ああ、なんてこった。ぼくの夏の夜は思いがけず消えてしまった。さびしい。ぼくはさびしいぞ。だれかこの寂しさを解ってくれるだろうか。
麦わらを買ってもらった

ぼくは眠っていた。すると突然目覚ましが鳴った。もう朝かよ、仕事に行かなくちゃ、と思ったが今日は休みだった。ベッドから這い出てぼんやりしていると、ヨッパライ某がやってきた。掃除機を直してくれという。以前取り替えたプラグがまたちぎれたのだ。休日の朝の過ごし方にふさわしいとは思えなかったが、ぼくは熱い珈琲を飲みながら掃除機を修理した。

予報によると今日は曇り時々雨とのことだった。晴れだったら行きたいところはたくさんあったが、雨だとそうたくさんは思いつかず、20キロほど北西にある小さな町に中元を届けに行くことにした。中元を届け、なれない挨拶をし、小さな町を後にした。車は例によって海の近くを南に走っていた。

昼食をとる前に海の近くの池に寄ってみた。どこかの学生たちが思い思いの場所にカンバスを立てていた。懐かしい油絵の具の匂いが漂っていた。

絵のことはさっぱりわからないが、これなんか、けっこうウマイんじゃないかと思った。

ヨッパライ某がザルソバを食べたいというので、ソバ屋に行った。


ソバを食った帰り道にスーパーに寄って買い物をした。その時、麦わらを買ってもらった。前回、海辺をぶらぶらしていたら、不覚にも日射病になってしまったからだ。ちなみに399えんだった
夜のジェット機
時計は11時を回っていた。風呂から上がって、屋上のベンチに腰掛け、雲が流れるのを眺めていた。涼しい西風が吹いている。予報では、あと数時間後には雨とのことだったが、星が瞬いている。テーブルにもたれて星空を眺めていると、遠くからジェット機が向かってきた。このままだと、ぼくの真上を通過する。ぼくはあわてて家の中に逃げ込んだ。もしジェット機が何か落としたら、ぼくに当たるかもしれない。家に入ってぼくは自分につぶやいた。お前、変わってるな。
夏の夜の本
家族三人で夕食を囲んでいると、ふいに息子が、何かおもしろい本はない?などと言い出した。ぼくは大皿に盛られたディナー(カボチャコロッケ)を箸でつかみながら、カラマーゾフの兄弟なんかどうや、夏の夜にぴったりやで。というと、相手はにわかに顔を曇らせ、あ、あれはちょっと、と首を振った。やれやれ、自称読書家、好きな作家は村上春樹、ではなかったのか。まあいい。夏の夜は探偵小説がお勧めだ。と言うわけで、本棚をごそごそやって、ディックフランシスの「興奮」「利腕」「大穴」を取り出した。彼くらいの年齢にはぴったりの探偵小説ではないだろうか。