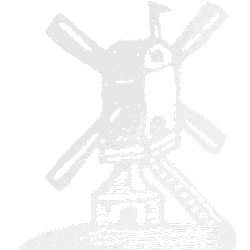昨夜、屋上に上がったぼくは、おもむろに人差し指を口に突っこみ、夜空を仰いだ。口から離れた指は、ひとすじの銀の糸を引いて天の一角を指した。
「明日は雨だな」
予報によれば、明日はおおむね好天らしい。しかし翌朝、つまり今朝、ぼくは雨の音で目覚めることになった。だからといって、ぼくは気象庁を責める気などない。気象の予測は大変デリケートなものである。高名な某カオス理論によれば、北京で蝶が羽ばたくとニューヨークで嵐が起こるという。これは取るに足らない些細な現象が、予測とまるで異なった結果を引き起こすという例えだ。つまり、気象を予測するならば、こういう下位レベルのデータまで入力する必要があるといっているのである。
では、今日の気象予測を外し、雨をもたらした「蝶の羽ばたき」に相当する些細な原因とは何だろう。
これである。昨夜は土曜であった。あちこちで乙女の住まう窓が開き、家に取り残された彼女らの、たっぷり水蒸気を含んだタメ息が上空に昇ったのだ。
エントロピー
通夜
黒い服を着込んで海沿いの道路を走る。
時計は22時を回った。夜の道路。
低くうなるタイヤの音が海鳴りのようだ。
夜を浸食した海が暗い道路を覆う。
海の底を走って死んだ人に会いに行く。
アカショウビン
店の棚を整理していたら、お客さんから借りたCDが出てきた。
「日本野鳥大鑑」
そのお客さんはまだ高校生。野鳥が好きだということだったので、「家の近くに毎年アカショウビンがきて鳴いていたのに、ここ数年、声がしなくなった」と、ボイスレコーダーに吹き込んであったアカショウビンの声を聞かせてあげた。彼はそれを憶えていて、次にコーヒーを買いにきた時、このCDを持ってきてくれたのだった。そのとき、彼はずいぶん疲れた様子だった。いまどきの高校生は勉強に忙しい。かわいそうに。「朝まで英字新聞で勉強してたんですが、文字が読めなくなって砂のように浮き上がり、こう、手ですくえるような感じに…」と、彼はカウンターに置かれた見えない英字新聞から文字をすくって見せた。その手がひどく年老いて見えた。特に驚くほどのことではない。ぼくもたまにあるのだが、彼はゲシュタルト崩壊を経験したわけだ。以来、彼はやってこない。季節は春。ぼくも冬は年寄りのようになる。彼は時々このブログを読んでいると言っていた。もし、これを読んだなら、返事をください。
花見
よく行く南の植物園のなかに立派な温室がある。入り口は自動ドアになっていて、冬に入ると、メガネが一瞬にして曇る。その大伽藍の一番奥に、食虫植物ばかり寄せ集めた場所がある。ウツボカズラ、モウセンゴケ、ハエジゴク。食虫植物は、その名の通り、虫の好む匂いを出して虫を呼び寄せ、捕食する。その、おどろおどろしいいでたちに、思わず眉をしかめる女性もいるだろう。しかし、虫を陥れんがために機能する無駄のないデザインには、死によって生を得る、究極の美学が見える。
桜の花が咲き始めた。ミツバチは花の匂い、色におびき寄せられ、集まる。それは桜にとって、子孫繁栄という大目的のための、必死の仕掛けである。生物は、子孫繁栄のために、なりふり構わない。
桜は人をも呼び寄せる。
自然界には、いろんなワナが、無意識に仕掛けてある。
春分の日
キューバ対ニッポンの野球があるらしい。なんと、決勝戦だそうだ。ニッポンって、そんなに強いのか。ぼくは野球に興味がないので、まるで関心がなかった。今日は祝日だし、日本国民は家でテレビの前に釘付けだろう。当然、お客さんは少ないに違いない。と、見当をつけ、朝からのんびり豆を焼いていた。しかし、ぼくの予想は外れた。朝からお客さんが多い。
「野球は見ないんですか?決勝戦らしいですよ」
中年の男性に聞いてみた。
「ああ、そういえば今日だったね」
涼しい顔でそうおっしゃる。意外だった。日本人は、みな熱狂的な野球マニアだと思っていたのに。後で気づいたのだけど、試合中にいらしたのはコテコテの常連さんばかりだった。
類は友を呼ぶということか。
ペパーミントブルー

麓にあるいつもの温泉を後にしたのが11時40分。山を越えて池田湖に向かった。その道は池田湖を左手に見下ろしながら緩やかに下っている。道半ば、見晴らしの良い公園があるので、そこでコーヒーを飲むことにした。とても静かな公園だ。時折、静寂を破ってウグイスの甲高い声が響き渡る。桜の下のベンチに腰掛け、開聞岳と、その向こうに続く空を眺めながらコーヒーを飲んだ。今日はまったく晴れ渡っている。どこまでも走れる気分だ。車は坊津に向かって走り出した。
坊津のふところにある小さな砂浜、丸木浜はひっそりしていた。その奥にある岩場に行くと、潮溜まりでウミウシがひなたぼっこしていた。海に切り立った崖の地層がおもしろかったので、しばらく観察した。
 車は左手に東シナ海を臨むリアス式海岸をくねくね走り続けた。今日の目的はやはりここだった。海に面したレストラン。そこにはオープンデッキがあり、海の音を聞きながらコーヒーが飲める。ここのマスターは器用なので何でも自分でやる。パンも自分で作っている。特に、ペンキ塗りは得意のようだ。例えば、プラスチック製の丸テーブルは青く塗ってある。わざとそうしたのか、かなり雑だ。ぼくは白のままでいいのにと思う。今日気づいた。いつのまにかウッドデッキもペパーミントブルーになっていた。
車は左手に東シナ海を臨むリアス式海岸をくねくね走り続けた。今日の目的はやはりここだった。海に面したレストラン。そこにはオープンデッキがあり、海の音を聞きながらコーヒーが飲める。ここのマスターは器用なので何でも自分でやる。パンも自分で作っている。特に、ペンキ塗りは得意のようだ。例えば、プラスチック製の丸テーブルは青く塗ってある。わざとそうしたのか、かなり雑だ。ぼくは白のままでいいのにと思う。今日気づいた。いつのまにかウッドデッキもペパーミントブルーになっていた。
ピラモール
第三日曜日は定休日。
カーテンを開けると「今日は何かいいことがありそう」と、思いたくなるくらい晴れていた。ダイニングに下りると、ぼくが昨夜セットしたフランスパンも、いい匂いに焼けていた。金もないし、ぼくはめったに繁華街に出ない。しかし、今日はブログでお世話になっているゆきちさんとべにこさんに会うため、天文館に出かけた。昨日と今日、ぼくらが使っているプロバイダ、SYNAPSE主催のイベントが行われているのだった。まるで、デートに出かける気分だった。アイロンのかかったズボンに、ぼくはもう一度アイロンをかけた。店に車をとめ、天文館に向かって歩きはじめた。20分後、急に人通りが多くなった。そこは天文館ピラモールというところだった。
「あ~、ずぷーんさんだぁ~♪」
歩いていると、べにこさんとそのお嬢さんに遭遇。かわいいお嬢さんに声をかけられ、ぼくはとてもハッピーな気分になった。春だなぁ♪
まず、ゆきちさんのブースに行ってみた。物販をやっている他のブースとは異なり、そこは彼女の撮った写真を貼り付けたパーテーションに囲まれた不思議な空間だった。ぼくは彼女の写真をネット上で見ていたのだけど、プリントされた色とりどりの花や風景は、春の天文館の空気にとけてなじみ、また違った存在感を放っていた。道行く人たちも、「きれいねー」と、足を止めて見入っていた。
つぎに、べにこさんのいるブースに向かった。そこではべにこさんのご主人が漬物を販売されていた。想像していた以上に甘いマスクのご主人で、少々意外だった(笑) ここでも、べにこさんのお嬢さんに100万ドルの笑顔で迎えられた。うれしかった。
買って帰ったお漬物は、さっそく頂いた。まず、「島津梅」という干し大根の漬物を食べたのだけど、これが食べだしたら止まらなくなって困った。一気に半分くらい食べてしまった。日本人なんだなぁ(笑)
朝の残像

最初のお客さんは、カメラマンの r 氏であった。
「マンデリンの浅煎りっちゅうのを飲ましてもらえないですか」
OK ぼくは、レンジに火をつけた。
コーヒーに湯を注いでいると、彼はカメラをドリッパーに向けた。
彼のカメラは、二度と戻ることのない一瞬を記録した。
未来と同様、過去は実在しない。
彼は深煎りのケニアを買い、天文館に向かった。
写真は「田園ぶらぶら写真館」館主rogi氏のものです。
魔女
毎朝コーヒー豆を焼く。それがぼくの日課だ。
今朝、いつものようにコーヒー豆を焼いていると、売り場に人の気配を感じた。売り場の明かりはまだ灯ってない。店は10時からだ。時計は9時30分を指している。
「一杯、飲ませてくれる?」
一目で高級品とわかる衣装をさりげなく着こなした年配の女性がカウンターに腰掛け、微笑んでいた。ぼくは照明のスイッチを入れ、コーヒーをたてた。
「きょう、お客さん、多いわよ」
カウンターにカップを置くと、彼女は意味深げに微笑んだ。
なにをおっしゃる。金曜日はたいていヒマなのだ。
と、そこに髪の長い女性が入ってきてコーヒー豆を注文した。開店10分前だった。
「マンデリンを1キロ」
それが始まりだった。以降、お客様は途絶えることなく、午前中にはいくつかのコーヒー豆が売切れ、夕方には、ほとんどのコーヒー豆が売り切れた。
もちろん、こんなことは滅多にない。