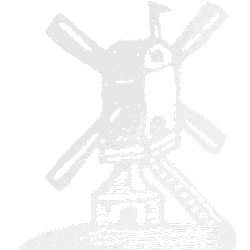男だったら一度はスパゲティーの茹でかたに狂うのではないだろうか。
1970年代、ぼくの青春はメタンガスのように無気力に広がっていた。その座標も方位もない不確かな世界に、ある日一つの数値が示された。ぼくの青春に深くかかわっていたのは料理だ。中学時代、ぼくの作る料理を食うために家に来る友達も少なくなかった。料理と言ってもたいしたものではなく、玉子焼き、お好み焼き、焼きソバ、焼き飯、ラーメン、などである。もちろん、スパゲティーもあったが、それは細いウドンにケチャップで赤色をつけただけの代物だった。そのころ読んだ伊丹十三著「女たちよ!」に、その数値は示されていた。12分。スパゲティーは12分茹で、わずかに芯が残る状態で取り出す。これをアルデンテと呼ぶ。ぼくはさっそくスーパーでスパゲティーの乾麺を買い、時計を睨みつつ慎重にスパゲティーを茹でたのだった。以降、それを供されるようになった友達からは尊敬のまなざしで見られるようになった。当然である。彼らの家では赤いウドンがスパゲティーだったのだから。