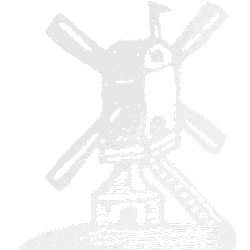はやくもLONG VACATIONは2日目に入ってしまった。数日前の予報では曇り一時雨とのことであったが、朝から思い切り晴れていた。そんなわけで、車は山を超えて海に向かっていた。行き先は笠沙にある例の海辺のレストラン。なぜそこに行ったかというと、お盆でも開いているかどうか気になったからである。行ってみると開いていた。しかも客が多い。少し意外であった。コーヒーを飲んで、次の目的地に走った。実をいうと今日の本当の目的は開聞山麓のハーブ園でハイビスカスシャーベットを食べることだったのだ。店に着いたのが4時。閉店は5時とのことだったが、ペルー風リゾットがセットになっているAランチを頼んだ。まだ昼ごはんを食べていなかったのだ。シャーベットは思ったとおり、とてもうまかった。ぼくはしみじみと食べた。これでぼくの夏も終わりである。ハーブ園を後にし、近くの某植物園に向かった。

この植物園では現在、「竹とうろうの夕べ」というイベントをやっていて、夜の10時まで園内をぶらつくことができる。ぼくは「竹とうろう」には興味がなかったが、夜中に園内をうろつけるのには興味があった。日が沈む頃、開聞岳が望める広場に行ってみたが、夕日はもう沈んだあとだった。せっかくなので写真を撮っていると、山頂付近を銀色に光る球形の物体が移動している!飛行機にしては小さすぎるし…。そうだ、アレはいわゆるひとつの、UFOだ!
ぼくは無我夢中でシャッターを切った。

クリックで拡大


A LONG VACATION 1日目

今日から夏休み。長いようで短い三日間のLONG VACATION.
その第一日目はスニーカーを洗うことから始まった。夏休みの一日目にはスニーカーを洗い、天日で干す。そう、これが清く正しいLONG VACATION第一日目の朝の過ごし方なのだ。
中略(酔っ払っていてうまく書けないので)
夕方、墓参りに行った。数年前から、ぼくも墓参りに行くようになった。ぼくは墓が嫌いだった。線香のにおいも大嫌いだ。でも、墓参りに行くようになった。歳を取ったせいかもしれない。
中略(酔っ払っていてうまく書けないので)
墓からの帰り、だれかがバーベキューをやろう、と言い出した。天気もいいし、わるくないな、と思い、すぐに賛同した。炭をおこし、照明の準備などをしているうちに材料が屋上に運ばれてきた。息子がいないので今日は家族3人で行った。いつものビールサーバーでビールを注ぐと、冷えてなかったのか泡ばかり出てきた。そこでぼくは宣言した。
「人生の四分の三はアワである!」
しかし聴衆の反応は鈍く、妻と娘のどうでもいい会話が一瞬途切れただけだった。
後略(以下同文)
ソバ屋は意外と遠かった

店を閉めた後、蕎麦ダイニング ニコラスというソバ屋に行ってきた。近いつもりで歩いていったら、けっこう遠かった。この店は、某弟が、先月くらいにオープンさせた店。らしい。実は、ぼくは知らなかったのだけど、たまたま某SNSで話題になっているのを見て一週間ほど前に知ったのだった。
そのSNSの記事を転載したページが公開されてますので、興味のある方はご覧になってください。

ところで今夜は、天気が良ければペルセウス座流星群が観察できますね。さっき夜空を見てみたんですが、雲間からカシオペアや白鳥座が顔を出してました。うまくいけば見られるかもしれません。月が沈むのを待ってます。
渋谷で暴れるカメ

今日は月曜で定休日。遊びにも行かず、朝から店に出かけ、焙煎機の煙突掃除をした。いつもは、お盆休みの初日に行うのだが、今回は盆休みをパーフェクトに休もうと思い、今日済ませることにしたのだった。午後2時過ぎに終了したので、店を閉め、車のオイル交換に行った。家に帰って、屋上で雲を眺めながらビールを飲んだ。夜の時間がたっぷりあるので、F少年から借りていたEARTHという映画を見た。そのカメラワークのすばらしさには舌を巻いた。何匹ものバショウカジキが小魚の群れをすごいスピードで追い回すシーンがあるのだけど、あの長いクチバシがカメラを回しているダイバーに刺さったら大変だと思い、見ていてハラハラした。極めつけは巨大なホオジロザメ。リアリティがすごい。あまりの恐ろしさに、ぼくは完全にフリーズしてしまった。このまま寝たら、絶対に悪い夢を見ると思い、気分なおしに、巨大カメが渋谷で暴れる映画を見た。なんとなく、すっきりした。
むし

ほとんどの女の子は虫が嫌いだ。チョウチョは好きよ、とか言っていながら、まず、さわろうとはしない。そして、キライな虫のチャンピオンが、ほぼ間違いなくクモである。いま、カタカナでクモ、と書いたのにはわけがある。そう、漢字の「クモ」という字は、それだけで嫌がられるからだ。そんなわけで、このブログにクモは登場しない。このブログは女の子も見ているから。でもぼくは虫が好きだ。子どもの頃はいつも虫を追いかけていた。今も追いかけているが、手にしていた捕虫網はカメラにかわった。虫の写真をこのブログに載せるのは、さっき言った理由で、いささか抵抗がある。でも、今回、登場させてみた。ちょっとグロテスクだけど、セミの写真。とても美しい。恐ろしいものを孕んでいるからこそ、美しいと感じるのだと思う。

P.S.
ふと思い出したのだけど、虫は苦手だけど、ダンゴムシは好き、という女の子はけっこういる。このダンゴムシ、堤防を猛スピードで走り回っているフナムシの仲間。ぼくはあのフナムシがとても苦手だ。台所にいる黒い虫に似てるじゃないですか。
お口直しに、花の写真でも。

妙な感じ
ゲゲゲの鬼太郎に妖怪アンテナがあるように、ぼくにも似たようなアンテナがある。そして今日は、それがしきりに反応する日であった。何かが起こる前触れなのか、すでに何かが起こっているのか。ぼくだけなんだろうか、この妙な感じは。やぁね
日本の土産
息子がホームステイに出かけて4日が経った。ぼくは彼がどこに行ったのかよく知らなかったので、彼が置いていったプログラムを見てみることにした。プログラムにはサンタローザと書いてある。ぼくは妻に聞いてみた。
ぼく「ねえ、このサンタローザって町の名前?」
妻 「知らない」
ぼく「たぶん、町のような気がするけど」
妻 「地図を見てみようか」
といって、妻は書棚から地図を取り出し、索引を調べ始めた。
妻 「あった。ブラジルだって」
ぼく「アメリカじゃないの?」
妻 「あ、カリフォルニアにもある」
ぼく「それだよ、たぶん」
二人で地図を覗き込んでみたものの、字が小さくて見つからない。
ぼく「あとでネットで調べてみるよ」
プログラムは4枚綴りになっており、半分は英語で書かれていた。ぼくは英語は2だったので、さっぱり分からない。日本語のうちの一枚は「準備リスト」になっていて、必要度が高いモノには◎、あれば便利、というモノには○印がつけてある。たとえば「◎ パスポート」「◎ 現金」といった具合。項目を上から順に見ていくと、下のほうに、「○ お土産」という欄があって、「日本の食品、風呂敷、お手玉など」とある。風呂敷、お手玉は分かるが、日本の食品って、いったいなんだろう。ぼくは真っ先に味噌汁と納豆が浮かんだ。でも、味噌汁は持っていくのが大変だし、納豆は生ものだから腐ってしまう。スルメとかカキピーあたりが良いのかもしれない。そこでぼくは想像の翼を広げ、日本の土産についていろいろ思い浮かべながら、ひとしきり楽しんだ。ところで肝心の息子はというと、イオンで買ったカキ氷機と舌が真っ赤に染まりそうな毒々しいシロップを土産に携え、旅立ったのだった。
星に願いを
あちなー
始めないことには始まらない
 |
|||||
 |
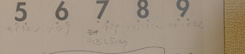 |
||||
 |
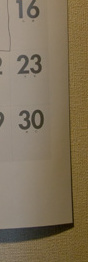 |
||||
 |
|||||
今年も盆休みが近づいてきた。休みはヒジョーにうれしいが、盆前にやらなくてはならない、めんどうな仕事がある。それは珈琲豆を焙煎する機械の分解掃除。けっこう難儀な作業で、一人でやると丸二日かかる。これを休みの日にやったら、ぼくのキチョーな休みは丸つぶれ。死ぬほど悲しい。と、いうわけで、去年から、盆前の数日間に、手分けして分解掃除をすることにしたのだった。というわけで、今日はサイクロンという機械の掃除をした。めんどくさい作業をするときのコツは、とにかく始めること。始めてしまえば、だんだんやる気が出てくる。これは脳の仕組みがそうなっているからであって、やる気のないことでも、やりはじめると脳の側座核が興奮し、やる気がグングンわいてくるのである。と、なんかの本に書いてあった。というわけで、お盆休みの案内です。13日(水)、14日(木)、15日(金)休みます。