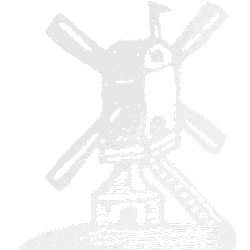店の電子レンジが黙り込んだのは枯葉の舞い散る秋の暮れだった。以来、ぼくの弁当はいつも冷えていた。秋の午後の冷えた弁当ほど切ないものはない。ぼくは一計を案じ、珈琲を焼く機械の上に弁当箱を載せ、少しでも温めようと努力した。しかしそれは倦怠期を迎えた男女の愛を少し上回る程度以上に温まることはなかった。
昨夜、ぼくは誕生プレゼントをもらった。それはミカン箱ほどもある段ボール箱だったので、それが密かに思い募っていたカメラでないことはすぐに分かった。箱の字を読むと、電子レンジ、と書いてあった。思えば、壊れた電子レンジも誕生プレゼントでもらったものだった。