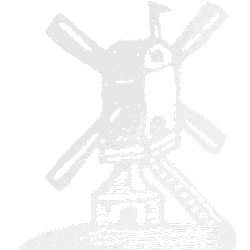昼前、豆を焼き終わって珈琲を飲んでいるところにオヤジが顔を出した。夜、何度も目が覚めてよく眠れなかったという。最近よく口にするのが、何もすることがない、楽しみがない、である。笑いながら言うので深刻な感じはないが、実につまらなそうだ。珈琲カップを置き、「友達も次々に死んで、遊ぶ相手もいなくなった」と、つぶやく。
昼前、豆を焼き終わって珈琲を飲んでいるところにオヤジが顔を出した。夜、何度も目が覚めてよく眠れなかったという。最近よく口にするのが、何もすることがない、楽しみがない、である。笑いながら言うので深刻な感じはないが、実につまらなそうだ。珈琲カップを置き、「友達も次々に死んで、遊ぶ相手もいなくなった」と、つぶやく。
ぼくの幼いころの記憶にはオヤジの友達がたくさん登場する。ぼくは男より女性と遊ぶほうが好きだったが、オヤジは男友達とよく遊んでいた。その友達が、ここ数年のうちに次々と死んでいった。そういう年齢なのだ。
「でも、Iさんは元気だぞ。まだまだすることがいっぱいあるみたいで忙しそうだ」
と、ぼくがいうと、オヤジの顔はにわかに明るくなった。
「俺が1番で、あいつは2番だったんだ…写真があるけど、見るか?」と自慢げに言った。何が1番なのか。学業成績ではないことは確かで「俺は裏口入学だったんだ」といつも得意になって話していた。
じゃあ見せて、と言うと、足取りも軽く店を出て行った。