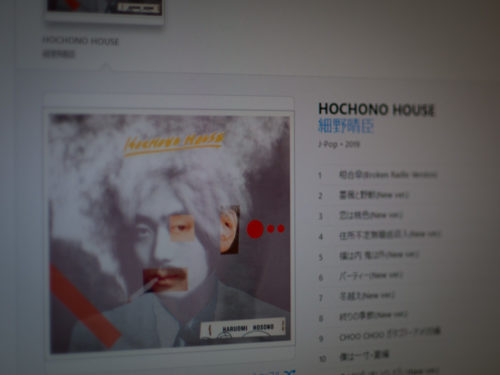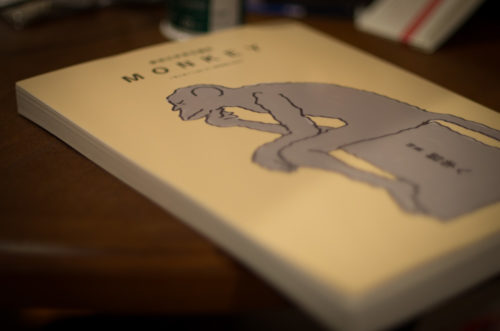夕食後、パソコンを開いてメールチェックをしていると、背後から何者かが急速に接近してきた。
ぷぅぅーーーーーん
奴だ。
おもむろにゴルゴ13の顔で立ち上がったぼくは洗面所の棚からヤツ専用の武器を手に取り、部屋に戻った。かわいそうだが奴には消えてもらう。背後からやってくる敵には容赦しない主義なのだ。
傘
月暈
さっき屋上で撮った月暈。このカメラ、おもちゃみたいだけど、けっこう使える
ぼやけた一日
昨夜は店の近くの駅ビルで映画を見た。終わったのが11時55分。帰って仕事を片付け、風呂に入り、ベッドにもぐりこんだのが午前2時。ちなみにグリーンブックという映画。
朝、トイレに行きたくなって起きたら頭はパアの状態だった。あと2時間寝たら正常になるはずだったのにベッドにつまづいて思いきり転び、壁で頭を打って目が覚めた
頭を打ったせいなのか視界がぼやけている。脳みそになにかまずいことが起きたのかもしれない。でも、天気がいいので、ドライブに出かけた
昼食は笠沙エビスで何か食べることにした。しかし辿りついてみると、なぜか休館日だった。しかたないので、いつもの漁港近くの寿司屋で、ヨッパライ某は安い方の寿司、ぼくはエビフライ定食を注文した。ここのエビフライはとてもデカい
お腹がふくれたので近くの丘に上り、昨日届いたおもちゃみたいなカメラで遊んでみた。360度撮れるということなので、カメラのシャッターを押す人も写ってしまう。つまり自撮りになる。それはちょっと恥ずかしいので三脚とリモコン(スマホ)を使い、離れたところからシャッターを切ってみた。ぼくが立っているところの先は切り立った崖。頭を打ったせいか視界が悪く、ちょっと怖かった
先日買った靴を早くなじませようと思い、峠で車を降り、山道を歩いて帰ることにした。マムシグサがたくさん生えていた
旧伊作街道。当時の舗装、石畳が残っている。苔が生えているので気をつけないと転ぶ。家に帰りつき、視界がぼやける原因が分かった。朝、寝ぼけて読書用の老眼鏡をかけてしまったのだ。頭を打ったせいではなかった
浮袋
微熱少年の夜
自分を知るには一生かかる
たとえば、の話。カメラを買うとする。まあ、これくらいの価格ならいいだろう、と自分に言い聞かせ、ネットの購入ボタンを押す。するとしばらくたってから、あ、予備の電池を買うのを忘れた、あ、ケースもだ、そうそう、あれも、これも、となって、かなり予算をオーバーする。なぜ買う前に気付かないのだろう。不思議だ
なんかもらった夜
愛される理由
考えれば不思議だ
ある雑誌の記事を読んで、今まで不思議とは思わなかったことが、急に不思議に思えてきた。以下抜粋
考えてみれば不思議なものだ。ある選択を行って、道が分岐し、そのときはそんなこともわからないが、それが自分の書くものに、あるいは自分の人生に、この上なく深い影響を及ぼす。それにまた、逃した機会というのも考えれば不思議だ。間違った選択を行い、何が起こりえたかはおそらく永久にわからず、何を逃したかもわからない、そういう瞬間。
ブライアン・エヴンソン 柴田元幸 訳
レイモンド・カーヴァーの「愛について語るときに我々の語ること」
その時々の選択によって道は分岐し、人生は変化していく。当たり前じゃないか。でも、筆者が言うように「考えてみれば」たしかに不思議な気がする。たとえば本屋で何気なく手に取った本が、その人の人生を大きく変えてしまう。よくあることだと思う。それはほんの一瞬のできごと
この記事が載っていた雑誌。表紙がおもしろくて買ってしまった