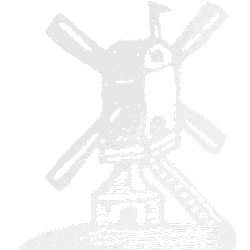時計は11時を回っていた。風呂から上がって、屋上のベンチに腰掛け、雲が流れるのを眺めていた。涼しい西風が吹いている。予報では、あと数時間後には雨とのことだったが、星が瞬いている。テーブルにもたれて星空を眺めていると、遠くからジェット機が向かってきた。このままだと、ぼくの真上を通過する。ぼくはあわてて家の中に逃げ込んだ。もしジェット機が何か落としたら、ぼくに当たるかもしれない。家に入ってぼくは自分につぶやいた。お前、変わってるな。
夏の夜の本
家族三人で夕食を囲んでいると、ふいに息子が、何かおもしろい本はない?などと言い出した。ぼくは大皿に盛られたディナー(カボチャコロッケ)を箸でつかみながら、カラマーゾフの兄弟なんかどうや、夏の夜にぴったりやで。というと、相手はにわかに顔を曇らせ、あ、あれはちょっと、と首を振った。やれやれ、自称読書家、好きな作家は村上春樹、ではなかったのか。まあいい。夏の夜は探偵小説がお勧めだ。と言うわけで、本棚をごそごそやって、ディックフランシスの「興奮」「利腕」「大穴」を取り出した。彼くらいの年齢にはぴったりの探偵小説ではないだろうか。
カッコーの巣の上で
エピローグ
熱いトマト
不思議の星
月夜のサソリ
ひと夏の物語
グレートギャツビー、物語としては特に目を瞠るものはなかったけれど、文体が秀でて詩的でロマンチック。ひねった比喩が多く、それがたまらなくいいのだけど、婉曲な表現が嫌いな人には読みづらいかも。語り手のニックは30歳にしては達観を得ているというか、どこか妙に醒めていて爺くさいといえば爺くさい。良い酒を味わったような、独特な読後感があって、満足度は高かった。
ハイヌーン
ぼくと僕
なぜかグレートギャツビーを読みたくなって、どうせなら村上春樹が訳したのを読もうと思い、熱帯雨林で調べると「一時的に在庫切れ; 入荷時期は未定です」となっていた。本音をいえば、字の大きさを自由に変えられる電子書籍で読みたかったのだけど、今のところ村上春樹の作品は電子化されそうにない。というわけで、野崎孝という人の訳した電子版をダウンロード。家に帰れば、この人訳の文庫本が息子の本棚にあったはずなのだが…専用のブックリーダーで読みつけると、ちょっと元には戻れない。

この作品は一人称「ぼく」で始まる。これが村上春樹訳なら、おそらく「僕」となる。「僕」と「ぼく」では、印象がずいぶん異なる。いうまでもなく、ぼくは「ぼく」がいい。なぜかしっくりくる。そんなわけで、この本は野崎孝訳でよかった、と、今は思う。まだ読み始めたばかりだから結論を出すには早いけど。ぼくがブログなどで「ぼく」を使うようになったのは、あるSFを読んでから。それはハインラインの書いた「夏への扉」
かくいうぼくも夏への扉を探していた。冬は、ぼくの心の中にあったのだ。