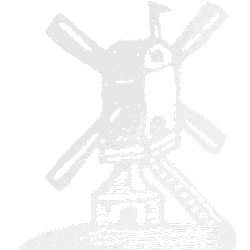それ以来私は一箇の漂泊者となった。そしてあの薄靄に包まれたすべての遠い丘の上に立った。その丘々もまた冷めたく堅く鮮やかだった。しかしかなた、もっと遥かなところには、またしても幸いに満ちた碧い遠方の風景が予感に溶けて横たわっていた、――さらに一層けだかく、さらに一層あこがれの思いをそそるように。それからもなおしばしば私は彼らの誘惑に出会った。私はそのまどわしに抵抗しなかった。彼らのうちに故郷を感じ、近い目前の丘にたいして他郷のものとなった。そして今私はそれをこそ幸福と呼ぶのである。かなたへと身を傾けること、広々とした夕暮れのおちかたに碧い平原をみとめること、そして冷ややかな近隣の地をしばしば忘れ果てること、それこそは幸福である。それは私が少年時代に考えていたのとはいくらか違った、何かしら静かなもの、何かしら寂しいものであって、美しくはあるが、笑いさざめくそれではない。自分の静かな隠栖の幸福から、私は次のような知恵を学んだ。それはあらゆる事物の上に隔たりの綿毛を残して置くということ、何ものをも日常平凡な接触の冷たい無残な光に当てないということである。そしてすべての物に軽く、そっと、注意深く、うやうやしく触れるということである。
これはヘッセの随想集、さすらいの記から抜粋したもの。今朝これを読んでいて、ふと以前このブログで紹介した、あの言葉を思い出した。「自分の故郷をいとおしむ者は、まだ未熟者である。どこの土地でも故郷だと思える者は、すでにひとかどの力ある人である。だが、全世界は異郷のようなものだとする人こそ完璧なのである」
これはサン=ヴィクトルのフーゴーという中世の哲学者の言葉だそうで、作家・翻訳家の田中真知さんが「故郷と異郷のはざまで」という記事で紹介されていたもの。ぜひ読んで欲しいのですけど、この記事に登場するケニアの友人の締め括りの言葉は、あの星の王子さまに出てくるキツネが言った、目に見えない、本当に大切な何かを指し示しているように感じられます。田中真知さんが記事の最後で「世界全体を異郷と思う感覚。それができる人が完璧かどうかは別として、日常生活をもふくめて、自己を取り囲む世界の一切が異郷に見える「とき」というのは、確かに存在する。しかし、そんなときぼくが感じるのは疎外感ではなく、むしろ存在という海のいちばん深い底にふれているような不思議に静かな感覚だ」と述べてます。この記事を読んで思うのは、本当に大切な何かは、ぼくのような不注意なものには永遠に隠されていて気づけないのではないか、ということ。でも、あきらめてはいけないですね。とても大事なことだから。ちなみに、ぼくの勘違いでなければ、この世界を異郷とする立場で語っている人を一人知っています。聖書の中のイエス・キリスト