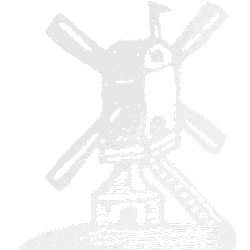植島啓司さんのコラムを読んでいて、次の文章に感銘を受けた。
生はとても優しく、静かで、捕まえることができない。力づくでは手に入らない。力づくでものにしようとすれば、生は消えてしまう。生を捕まえようとしても、塵しか残らない。支配しようとしても、愚か者の引きつり笑いをする自分の姿が見えるだけ。生を欲するのなら、生に向かって、木の下にやすらぐ鹿の親子に近づくように、そっと、歩を進めなくてはいけない。身振りの荒さ、我意の乱暴な主張が少しでもあると、生は逃げていってしまい、また探さなくてはならなくなる。そっと、優しく、かぎりなく繊細な手と足で、我意をもたない自由で大きな心で、生にまた近づいていって初めて、生と触れあえる。花はひったくろうと手をのばすだけで、人生から永遠に消えてしまう。我意と貪欲に満ちた気持で他人に近づいてゆくと、手の中に掴むのは棘だらけの悪魔で、残るのは毒の痛みばかり。
しかし、静かに、我意を捨て、深い本当の自己の充溢とともに他人に近づくことができる。人生で最上の繊細さを、触れあいを知ることができる。足が地面に触れ、指が木に、生き物に触れ、手と胸が触れ、体全体が体全体と触れる。そして、燃える愛の相互貫入。それこそが生。わたしたちは皆、触れることで生きている。
これはD・H・ロレンス「チャタレー夫人の恋人」第2稿の一節、だそうです。ぼくは比較的、長い時間生きているけど、今つくづく思うのは、この文章にあるようなこと。ぼくが日々足を棒にして探しているものは、遠い異郷にあるようなものではないのです。