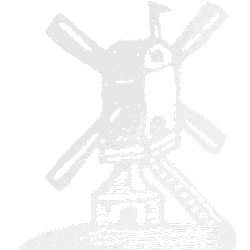映画のようなアメリカ
ネットでオバマ大統領の演説を見た。
政治に疎いぼくでも感動した。
まるで映画の1シーンを見ているようだった。
アメリカとはなんだろう。
それは、またとない幻影の国。
だからアメリカは甦る。映画のシナリオのように。
キミたちのニンジン
ある日、ぼくの目の前からニンジンが消えた。
目の前にニンジンがないと、ぼくは走れない。
「オレのニンジンはどこに行った」
必死でぼくはニンジンを探しはじめた。10年くらい前の話だ。
でも、最近になって、ぼくは気づいた。
「ニンジンを探すことが、オレのニンジンかもしれない」
そう、「求めよ」がぼくのニンジンだったのだ。
きょうの内田樹さんのブログを読んでて、フトそんなことを思いました。
ヒマな方は読んでみてください。
ちなみにぼくはニンジンがキライですがよ。ウマじゃないし。
湯治な一日

寒い日が続いたせいで、店のコンクリートの床がコチコチに凍りつき、ぼくのデリケートな足の指に赤いしもやけができてしまった。 そこで、そんなかわいそうな足の指をいたわってやろうと思い、指宿の某温泉に行くことにした。いつもの温泉に行くと、八つある湯部屋のうち、縁の湯と恵の湯が空いていたので、今日は縁の湯を選んでみた。湯舟の隅に石臼が据えてあって、そこから温泉が流れ出している。うーん、これはいい。このつぎ家を建てるときは、わが家の風呂もこんなふうにすることにしよう。
そこで、そんなかわいそうな足の指をいたわってやろうと思い、指宿の某温泉に行くことにした。いつもの温泉に行くと、八つある湯部屋のうち、縁の湯と恵の湯が空いていたので、今日は縁の湯を選んでみた。湯舟の隅に石臼が据えてあって、そこから温泉が流れ出している。うーん、これはいい。このつぎ家を建てるときは、わが家の風呂もこんなふうにすることにしよう。
かわいそうな足の指がふやけてきたので、いつもの温泉を後にし、湖を半周していつものハーブ園に行き、いつものランチを食べた。

こうしょっちゅう行っていると、まるで自分の家のような気がしてくるから不思議だ。

ぼくです

ドーナツも好きですが、シュークリームも大好きです。
よろしく
P.S.
なお、この似顔絵?は特別にお願いして作っていただいたものなので、たぶん、どこにも売ってません。
追伸2
作ってくださった、ちくちく日記のこばなさんが記事にしてくださいました。
罠

某コーヒー店の屋上には菜園があって、今、水菜、春菊、サニーレタスなどが収穫の時期を迎えている。昼前、その菜園の管理人がコーヒーを飲みに来た。管理人はカウンターにカップを置くと、ふいに七人の侍に出てくる貧乏百姓のような表情になってつぶやいた。
「せっかく植えた豆の芽が全部食われちまった」
「ふーん、ハトに?」
「いや、ここいらでは見かけない、変な鳥だ」
そういえば、ぼくも今朝見たのだった。電線に止まって1分おきにクソをする変な鳥を。よく見ようと思って近づいたら、ギー、と鳴いて飛び去った。もしかするとこれがウワサのネジマキ鳥なのかもしれない。
「それでオレはな」と、管理人は続けた。
「ワナを仕掛けてやった」
と言って、黒澤映画に出てくる小悪党のようにニヤリと笑った。
昼すぎ、ぼくはそのワナを見に行ったが、まだ何もかかっていなかった。
オトコの座標
世界はオトコであふれてる。
世界はオンナであふれてる。
と、いうわけで、ぼくは自分のオトコとしての座標を確認するために、次のページにアクセスしてみた。
「あなたのモテ力をリアルにテスト」
http://girls.channel.or.jp/wdp/
すると、次のような結果が出た。

あなたはまるでサーカスの団長のように男ゴコロを上手に操るすご腕! めちゃめちゃモテるでしょ?そのカワイイ笑顔と計算つくされた男たちへの対応は生まれもった才能。 ただ、定期的に男ゴコロを読む力をトレーニングしないとその力は衰えていきます。。最新の男事情をチェックすることを心がけて!
どうやらぼくはオトコとして標準的な位置にいるらしい。
※なお、ぼくの環境ではFirefoxだとうまく働きませんでした。
IEだとOKでしたがよ。
Vaya Con Dios
ぼくらはみんな生きている

昨夜はニンニクの効いたモツナベを食った後、お客さんからお借りした「潜水服は蝶の夢を見る」という映画を見た。これは同名の著書を映画化したもの。以下、アマゾンの著書紹介から。
———–ここから————-
著者のジャン=ドミニック・ボービー氏は、1952年生まれ。ジャーナリストとして数紙を渡り歩いた後、世界的なファッション雑誌、『ELLE』の編集長に就任しました。名編集長として名を馳せますが、1995年12月8日、突然脳出血で倒れ、ロックトイン・シンドロームと呼ばれる、身体的自由を全て奪われた状態に陥ってしまったのです。まだ働き盛りの43歳でした。病床にありながらも、唯一自由に動かせる左目の瞬きだけで本書を「執筆」しました。本書は大きな話題を呼び、フランスだけでなく、世界28か国で出版される世界的なベストセラーとなりました。しかし、1997年3月9日、突然死去。本書がフランスで出版されたわずか2日後のことだったのです。
———–ここまで————-
さて、突然ですが、みなさんは生きている、という実感を味わったことがあるでしょうか。おそらく、気がついたらすでに生きていたはずなので、つまり、生きている状態がふつうだったから、特にそう感じたことは案外ないかもしれません。一度死んでみたら分かるのでしょうけど、なかなかそういうわけにもいきません。ところで、失うことで得るもの、あるいは、失わないと得られないものって、ありますよね。映画の主人公は、突然、身体的自由を全て奪われてしまったわけです。ぼくは勘繰るのですが、きっと、彼は何かを得たに違いありません。それは、もしかするとぼくたちが一生かかっても手に入れられない何かで、しかも、それは人が人生すべてをなげうってでも得るべきであろう、何か。それはたとえば、ヨブ記のヨブが苦難の末に悟った何か。ぼくはこの映画を見ていて、そんな気がしました。
蛇が出るまで口笛を吹け

夜、口笛を吹くとどうなるか。
蛇が出る。これが正解だ。
では、雪のちらつく寒い日に穴を掘るとどうなるか。
からだが温まる。これが正解だ。
異論はあるかもしれないが、気にしなくてもよい。

わが家の庭には、穴を掘ったあとが無数にある。なぜなら、ぼくが穴を掘ったからだ。なお、月にも無数の穴があるが、それは別の問題である。そして雪のちらつく今日の午後、ぼくは青空が出るのを待って庭に穴を掘りはじめた。すると、いつものように2階のベランダからネコがしつこく語りかけてきた。訳するとこうだ。
「何をしているんだ」
「俺を埋める気か」
「俺が何をしたというんだ」
ぼくは答えた。
「うるさい、自分の胸に聞いてみろ」
ぼくにはいちいちネコの相手をしているヒマはない。
ぼくにとって休日の時間は貴重なのだ。
今朝、某アマゾンに注文しておいた本が届いた。
ブラッドベリの「たんぽぽのお酒」。
ぼくの貴重な時間は、こういう本を読むのに費やされる。