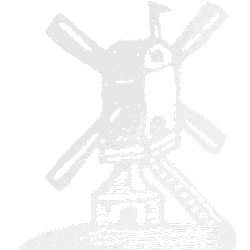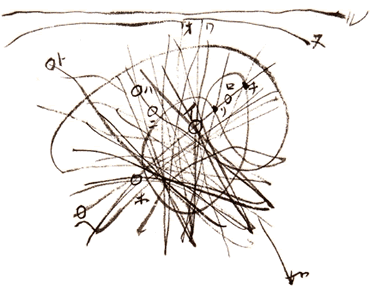ひさしぶりに海に来て、だれもいない波打ち際を歩いた。

どこまでもどこまでも歩いていると、水際にきれいな白い鳥がいた。
写真を撮ろうと思って、そうっと近づいていった。
でも飛んでいった。

数日前の、某ブログの記事を思い出した。
———- ここから ———-
私は自分が若い日に傾倒した哲人の言葉を思い出していた。正確な言葉ではないが、子どもの教育にも打ち込んだその哲人は、子どもから、「わたしはリスが好きなのに、わたしが近づくとリスは逃げてしまいます。どうしらたいいのですか」と問われた。彼の答えは意外なものだった。そしてその答えは、私の心にずっと残った。彼の正確な言葉は忘れたが、こんなふうに答えた。「リスがきみに安心感が持てるように、毎日リスのいる木の下でじっとしていなさい。何日も何日も。」 その奇妙な答えは彼自身が自然のなかの暮らしで実践していたものだった。大樹の下で禅定ともなく静かに日々座って、リスや山の動物たちが彼を恐れなくなるまで慣れさせ、そしてやがて彼の体にリスが乗り駆け回るようまでなった。猿がやってきて握手を求めたともあった。
猿の握手。私はそんなバカなと思ったが、別途動物学の本で、仕込んだわけでもなく自然の猿にそういう習性があるのを知った。

明日は晴れらしいね
三分咲き
ひとりの部屋
時間と必然
おととい傘の中の二人
某営業マン
ショーシャンクになれなかった

しまった、パトカーだ!
ぼくは車を急転回させ、民家が軒を並べる狭い路地に逃げ込んだ。背後でサイレンがけたたましく鳴り響く。ぼくは最初の十字路を左に折れ、目についた高級住宅のコンクリート車庫に車を突っこみ、シャッターを下ろした。
と、そこで目が覚めた。いやな夢だ。

今日は雨のはずだった。しかし、カーテンを開けると、空はどんより曇っているものの雨は降っていない。
くそっ。
ぼくは舌打ちした。週間予報では今日は雨だった。そのつもりで、きょうはショーシャンクな一日を計画していたのだ。つまり、指宿の某貸切温泉の外湯に浸かり、全身に雨を受けながら喜びに満ちた顔で空を仰ぐ予定だったのである。

しかし、あきらめるのは早い。もしかすると指宿は雨かもしれない、と思って、とりあえず車を走らせた。が、天気はますます良くなり、雲間から青空が見えはじめた。ショーシャンクな計画は失敗に終わったのである。
天気が良くなってきたので某植物園まで足を延ばし、そこで食事をとることにした。温泉横の山を超えて池田湖を半周し、しばらく走るとそこが植物園だ。つづら折の坂を上りきると空が開け、気分も明るくなってきた。が、そこには黒白ツートンカラーの車が待ち構えていた。ちなみにスバル・レガシーターボ。
「どちらへ行かれるんですか?」
車を止め、窓を開けると、背筋のピンと伸びた立派な体格のお兄さんがニコニコしながら聞いてきた。
ぼくの顔は思い切り引きつっていたが、となりのヨッパライ某がうまく応えてくれた。まったく心臓に悪い。

植物園の花壇に、きれいなキャベツが噴水のように植えてあった。

ここのチューリップ畑はほんとにきれいだ。
いつかわが家の庭もこんな風にしようと思う。

レストランで昼食。
ホワイトクリームと焼サーモンのスパゲティーなんとか。

ガラスのつぶやき

ガラスのお雛さまは、透きとおった目で、一日中、雨を見ていた。
「はやく雨になりたいな。いつになったら雨になれるのかな」
※写真のお雛さまたちは、某コーヒー店の下にあるRANというギャラリー喫茶で展示販売中です。
骨の記憶
店からの帰り道、いつものようにカーラジオのスイッチを入れたら、不思議な音のする楽器がバロック風の音楽を奏でていた。木管楽器らしいのだけど、今まで聞いたことのない音。聞いているうちに、これは動物の骨で作った楽器じゃないだろうか、と、ぼくは思いはじめた。聞けば聞くほど、そういう音に聞こえる。風が吹いた翌朝、海に行って波打ち際をぶらぶら歩いていると、流木に混じって、白く脱色した大きな頭骨が打ち上げられていることがある。肉が無いので、それがどんな生物のものなのか分からない。馬かもしれないし、海に棲む怪物のものかもしれない。ぼくはラジオから流れてくる音楽を聞きながら、そんな波打ち際の風景を思い浮かべていた。その、持ち主の知れない頭骨に穴を穿って楽器にすれば、きっとこんな音がするだろう。音楽が終わって、曲の紹介があった。曲名は、バッハのなんとかカンタータ。楽器は、オーボエ・ダカッチャ、だそうで、それが動物の骨で作ってあるかどうかは説明されなかった。