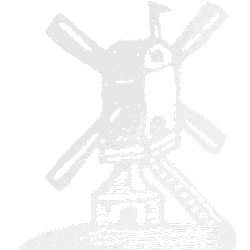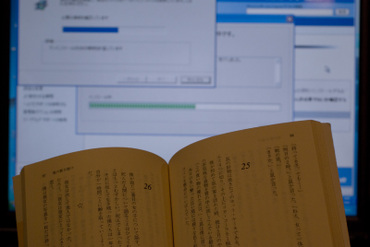今日は休みだったけど、リカバリ疲れか、具合が悪くて家にいた。
屋上でボーっとしてたり、庭の草花の写真を撮ったり。
ああ、たまには長い休みをとって、どこか遠くへ行きたいな。
どうせ行くんなら、ピラミッドのあるエジプトがいいな。
オーロラの見えるフィンランドもいいね。
ま、とりあえず、ハワイでもいいや。
ハワイに行ったら、あの歌を歌いながら、海辺を歩こう。
カメハメハーカメハメハーカメハメカメハメハ

いつの間に
りかばり終了間近
リカバリ中につき・・・
春分の日だというのに、突如、パソコンが冬眠してしまった。
今やっとこうしてネットにつながったところ。
コメントの返事、遅くなってすんません。明日書きます。
Jung
(笑)
あなたは笑ったことがあるだろうか。白状するが、ぼくは笑ったことがない。子どもの頃、笑う練習がぼくの日課だった。それは苦しい毎日だったが、おかげで笑うフリに於ては誰よりもうまくなった。笑うことができなければ、この渇ききった砂漠のような都会で生き抜くことは難しい。この件に関しては、いずれ機会を改めて詳しく語ってみたいと思う。
話を戻そう。たとえば対人関係の場合、肝要なのは、まずどこで笑うか、である。目の前の相手が笑うべき言動をとった際、それがどの程度の笑いに相当するか速やかに判断し、いくつかのバリエーションの中から適切な笑いを選んで効果的に実行しなければならない。よくあることだが、相手が白けたジョークを放った場合などには、いわば思いやりから笑ってあげる必要が生ずる。しかし、いずれにせよその判断は人生哲学に裏打ちされた優れた人間観察能力がないと行えない。つまり、笑いのセンスがこれである。
笑いにもいろいろあるが、第一回目の今日はジョークについて考えてみることにしよう。テキストとして、角川文庫ポケット・ジョーク第一巻から次のものを選んでみた。
夫 「ぼくはいままで一度も浮気なんかしたことがない。きみも同じことが言えるかい?」
妻 「ええ。でもそんな真面目くさった顔ではむりだわ」
どうだろう。笑うことができただろうか。もしあなたが一角の成人でありながら笑えなかったとしたら、すでに問題があるといえる。対策を考えたほうが良いだろう。
以下、次号につづきません。
窓
ある月曜日
山の向こうに何があるのだろう。たぶん、だれも知らない。少なくともぼくは知らない。冒険はいつもこのようにして始まる。そしてぼくは今日も美しい白馬にまたがって山を超える。ような気分で汚れて灰色になった白い車のアクセルを踏んだ。

山を下って信号を右折し、まっすぐ走っていくとそこは海。海の向こうに何があるのだろう。たぶん、だれも知らない。少なくともぼくは知らない。しかし、今日はそんなことはどうでも良かった。遠い目で海を眺めながら、お客様から頂いたリエットをおごそかにパンに塗りつけて食べるのが今日の目的なのだから。その前に海の写真を撮ってこようと思い、海に面した岸壁に車を止めた。

「写真を撮ってくるからパンを切って準備していてくれ」と、となりのヨッパライ某に言い残し、海岸に出た。写真を撮って車に戻ると、ヨッパライ某がうれしそうな顔をして「ニュースがある」という。ぼくはイヤな予感がした。
「リエット、忘れちゃったー」
実にすばらしいニュースだった。パンだけではあまりに悲しすぎるので、車はUターンし、某食堂に向かった。1050円の定食を食べ終えると車は近くのカメが多か、という丘に上っていった。

その丘の眺めのいい展望所には桜を植えた庭園があり、池があった。カメはいなかったが、オタマジャクシが1600匹近く泳ぎ回っていた。


帰りに海浜公園に寄って、しばらく池を眺めていた。