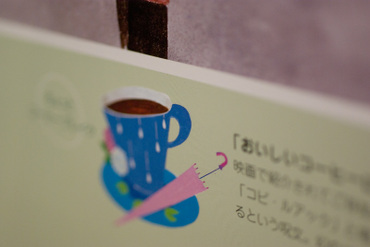アジサイの写真を撮っていて、ふと思った。
子供のころ画用紙に描いた雨の色は青だった。なんでだろう。
そうか、水色か。
太陽は赤く、水の色は青だった。
そういえば、恋は水色、なんて曲があったっけ。
でも、なんで恋が水色なの。涙の色?
ま、いいや。
アジサイの青って、雨に似合うよね。
それが言いたかっただけ。
ぼくの白い花
急いで家に帰ったわけ

ここ数日、ぼくは庭に置いた小さな水鉢を熱心に覗き込んでいた。昨年暮れ、ぼくは珈琲を買いに来るお客さんからスーパーの袋に入った泥のかたまりをいただいた。それを教わったとおりに水鉢の底に沈め、毎日飽きることなくそれを眺めていた。やがて泥のかたまりは芽を吹き、丸いつやつやした葉を水面に広げていった。
一週間前、ぼくは水の底に小さな蕾らしきものを認めた。それはみるみる大きくなって、水面に頭をもたげ、そして今朝、まるで定時を知らせる精妙なからくり時計のように、おもむろに膨らみはじめたのだった。ぼくは急いで鞄からカメラを取り出し、その様子を記録した。しかし、すでに家を出る時刻をかなり過ぎている。ぼくは遅刻を恐れるサラリーマンよろしく、開きかけた花を後に家を出たのだった。
帰宅し、駐車場に車を停めると、ぼくはまっすぐに水鉢に向かった。完全に開いた白い花を見るために。

道は星の数
ぼくが住んでいる皇徳寺から川辺町(南九州市)へ行く道は、いくつもあるけれど、ぼくのお気に入りは、川辺ダムを経由していく道。景色が開けているし、交通量が少ないこともあって、気分よく走ることができる。途中、川辺ダムに車を停めて、コーヒータイム。

大きな地図で見る
初夏の日差し、空は秋色

デジイチに古いレンズをくっつけて、ドライブに出かけた。

古いレンズだから、ピントは手で合わせる。時間はたっぷりあるので、のんびりとピントを合わせる。遅いからといって、だれも怒ったりしない。風の音、鳥の声、川の流れる音。今日は、いつもとコースを変え、ダムの横を通って南九州市の岩屋公園に走った。

川のそばのベンチでランチタイム。パンに手作りリエットをはさんで食べる。珈琲はもちろん、某珈琲店の珈琲。

アサーッ! なわけないか

このはし、渡るべからず。

崖になにか彫ってある。

帰りに、中山インターチェンジ近くの園芸屋さんでアイビーゼラニウムというのを買った。

できたら
読んでから見る?
バチカンを舞台にしたサスペンス、ダン・ブラウン著「天使と悪魔」が映画になって昨日公開された。ぼくは今それを本で読んでいる最中なんだけど、当然というか、本の中で活躍する主人公の顔と声が否応なくトム・ハンクスになってしまう。数年前に読んだ同シリーズ「ダ・ヴィンチ・コード」の時は、それが映画化されることを知らずに読んだため、主役の某大学教授の顔はトム・ハンクスになることはなかった。トムでも悪くないんだけど、なぜか彼はぼくの中ではコメディアンに分類されていて、つい、ビル・マーレイ主演の「ゴースト・バスターズ」のような展開を想像してしまう。そう、クライマックスでマシュマロマンが現れ、教会を踏み潰すというアレ。かなり古いけど。

朝の声
雨の日のカップ
そうめんが好きでない人もいるらしい
一昨日、そうめん流しに行ったばかりだというのに、今日の夕食はそうめんであった。もし明日の夕食がまたそうめんであったとしても、ぼくは文句は言わない。かもしれない。そう、日本人は誰しも、そうめんが好きなのだ。と、ぼくは思っていたのだが、そうではないことが判明した。確率で言うと、15人に1人の割合で、そうめんを好まない。かもしれない。(ぼく独自の調査による)
ぼくは、悲しい時や、辛いことがあった時、「そうだ、こんな時は某町営そうめん流しに行って、気分転換を図ろう!」と思うのだが、そうめんを好きでない人は、たぶん、それができない。これは不幸なことではないかと思う。