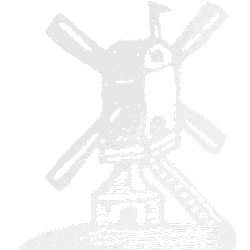一週間前、デジイチが壊れた。でもそれは少しも悲しいことではなかった。ぼくはデジイチから開放され、少し自由になった。それはちょうど、2年間つき合った恋人に別れを告げた時、彼女の後ろに広がる空が不思議なくらい高かった。そんな感じだった。少しだけ悲しかったのは、デジイチ用に買い求めた部品が、デジイチが壊れた次の日に届いたことだ。
やっぱりハッピーエンドがええな
らしくない?
 |
|||
 |
 |
||
トイレの横には来月開催されるクラシックコンサートのポスターが貼ってある。毎年のことだから、常連のお客さんは、特に気にすることなく普通に眺めていらっしゃる。
最近、店の柱に、ロックコンサートのポスターが貼られた。それに気づいた常連のお客さんたちは、え? という顔になって、ポスターの前に歩み寄り、なぜか首をかしげている。
嘘つき! と彼女は言った。
ぼくは悔しい。なぜなら昨日、ぼくはひとつも嘘をつかなかった。
ところで、嘘といえば村上春樹のイスラエル文学賞受賞演説を思い出す。いわく、隠れている真実を嘘の上におびき出すのだ。
そして、村上春樹といえば某作品の次の場面。
「ねえ、私を愛してる?」
「もちろん」
「結婚したい?」
「今、すぐに?」
「いつか・・・・・・もっと先によ」
「もちろん結婚したい」
「でも私が訊ねるまでそんなこと一言だって言わなかったわ」
「言い忘れてたんだ」
「・・・・・・子供は何人欲しい?」
「3人」
「男? 女?」
「女が2人に男が1人」
彼女はコーヒーで口の中のパンを嚥み下してからじっと僕の顔を見た。
「嘘つき!」
と彼女は言った。
しかし彼女は間違っている。僕はひとつしか嘘をつかなかった。
蘇る金狼少年

ウソをつくのはもうやめよう。そう決心して一年がたった。思えば長かった。ウソをつかない毎日は、それまで平気でウソをついていたぼくにとって煉獄のような日々であったが、なんとか持ちこたえることができた。そう、これはぼくのように、味のしない野菜スープを毎朝欠かさず飲むなどしつつ、インドの山奥の苦行僧のように、日夜厳しい修練を積んだ者にしかできないことなのである。もしあなたがぼくのマネをして、私も今日から絶対にうそは言いません、と宣言するなら、ぼくはやさしく諭すであろう。あなた、ウソを言ってはいけませんよ
たい焼きの逆襲
夜の庭
オカシーお菓子
かーちゃん、ただいまー、おなかペッコペコだよ、なんかある?
あるわよぉ~、テーブルを見てごらん

あ、スゲーや、ぜんぶ食べてもいいの?
いいわよぉ~
わーい! かーちゃんありがとう! ガブッ !?

か、かーちゃん、ひどいよ、カラッポじゃないか、ううう…
もう、ぐれてやるー ダーッ
機内誌の記事で、こんなお菓子を見つけ、ぜひ食べたいな、と思っていたら、常連のサカモト教授が「帰郷した時に買ってきてあげる」ということになって、本日いただきました。とてもおいしいです。ありがとうございます。また買ってきてください。

さらば冬の巨人
市長ブログ
一ヶ月ほど前、珈琲を仕入れにいらした阿久根市のお客さんと、いろんな話をしているうちに阿久根市長の話になった。おもしろい人物ですよ、ということで、ぼくも興味を持った。以来、毎日のように「阿久根市長ブログ」を読んでいるのだけど、ぼく的にウケまくりの内容だ。おもしろい。ブログのおもしろさの一つは、書いた本人の肉声に近いものが直に味わえるところにある、と思うのだけど、阿久根市長ブログにはそれがある。かなりヤバイ(笑) 阿久根市長のやってることに対しては、いろんな意見があると思う。ぼくも、市長のブログだけ見て意見を言うわけにはいかない。やはり自分の足で現場に行き、市民のナマの声を聞かなくてはなんともいえない。さっき、今日のブログ記事を見てみたら、日経ビジネスオンラインのインタビュー記事にリンクが張ってあり、そこに市長の言わんとするところがうまくまとめられていた。興味のある方は、ご覧になってみてはいかがでしょう。