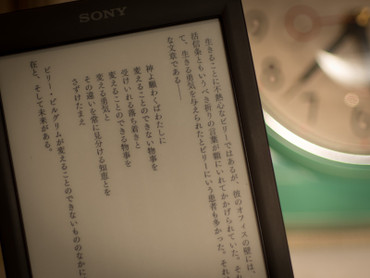朝から雨が降っていた。春の雨。ちなみに晩飯のおかずは春雨だった
朝から雨が降っていた。春の雨。ちなみに晩飯のおかずは春雨だった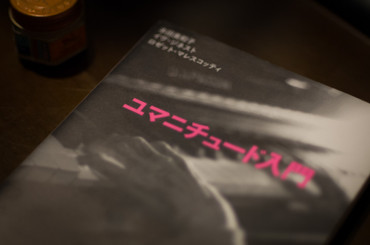 仕事の合間に、お借りした本を読んだ。読む本にもよるけれど、やはり読書は大事だな、と思った次第。以下、本文より
仕事の合間に、お借りした本を読んだ。読む本にもよるけれど、やはり読書は大事だな、と思った次第。以下、本文より
「ユマニチュード」という言葉は、フランス領マルティニーク島出身の詩人であり政治家であったエメ・セゼールが1940年代に提唱した、植民地に住む黒人が自らの“黒人らしさ”を取り戻そうと開始した活動「ネグリチュード(Negritude)」にその起源をもちます。その後1980年にスイス人作家のフレディ・クロプフェンシュタインが思索に関するエッセイと詩の中で、“人間らしくある”状況を、「ネグリチュード」を踏まえて「ユマニチュード」と命名しました。 さまざまな機能が低下して他者に依存しなければならない状況になったとしても、最期の日まで尊厳をもって暮らし、その生涯を通じて“人間らしい”存在であり続けることを支えるために、ケアを行う人々がケアの対象者に「あなたのことを、わたしは大切に思っています」というメッセージを常に発信する… つまりその人の“人間らしさ”を尊重し続ける状況こそがユマニチュードの状態であると、イヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティは1995年に定義づけました。 これが哲学としてのユマニチュードの誕生です。
ユマニチュードを紹介したテレビ番組。劇的な展開に思わず目を瞠ります