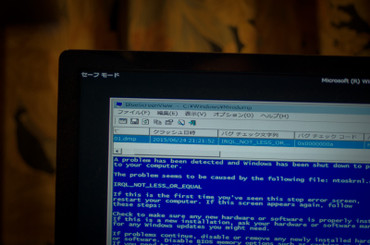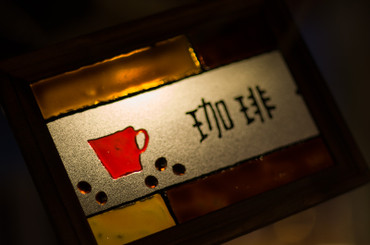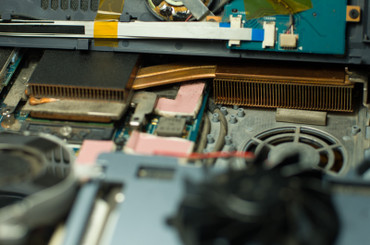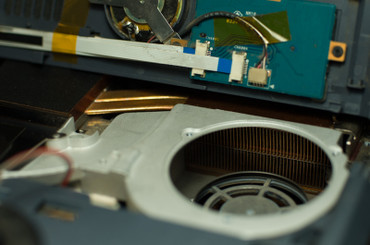午前9時55分。間もなく店を開ける時間。BGMをONにし、店内の照明のスイッチを入れる。次に、店の奥にあるcoffeeのネオンサインのプラグをコンセントに突っ込む。あれれ? 点灯しない。ガーン!ついに壊れてしまったのか。毎日ずっと点けっぱなしだったからなぁ。念のため、コードの途中に付いているスイッチのON、OFFを繰り返してみた。すると一瞬、ネオンが光った。さらにガチャガチャやってると、ネオンはいつものように点灯した。やっぴー! ここのところの長雨でスイッチが錆びたのかもしれない。そういえばその昔、テレビが映らなくなるとテレビの箱をたたく人がいた。TとかUとかBとか。ん?なぜかみんなO型じゃん。たまたまだろうけど
午前9時55分。間もなく店を開ける時間。BGMをONにし、店内の照明のスイッチを入れる。次に、店の奥にあるcoffeeのネオンサインのプラグをコンセントに突っ込む。あれれ? 点灯しない。ガーン!ついに壊れてしまったのか。毎日ずっと点けっぱなしだったからなぁ。念のため、コードの途中に付いているスイッチのON、OFFを繰り返してみた。すると一瞬、ネオンが光った。さらにガチャガチャやってると、ネオンはいつものように点灯した。やっぴー! ここのところの長雨でスイッチが錆びたのかもしれない。そういえばその昔、テレビが映らなくなるとテレビの箱をたたく人がいた。TとかUとかBとか。ん?なぜかみんなO型じゃん。たまたまだろうけど